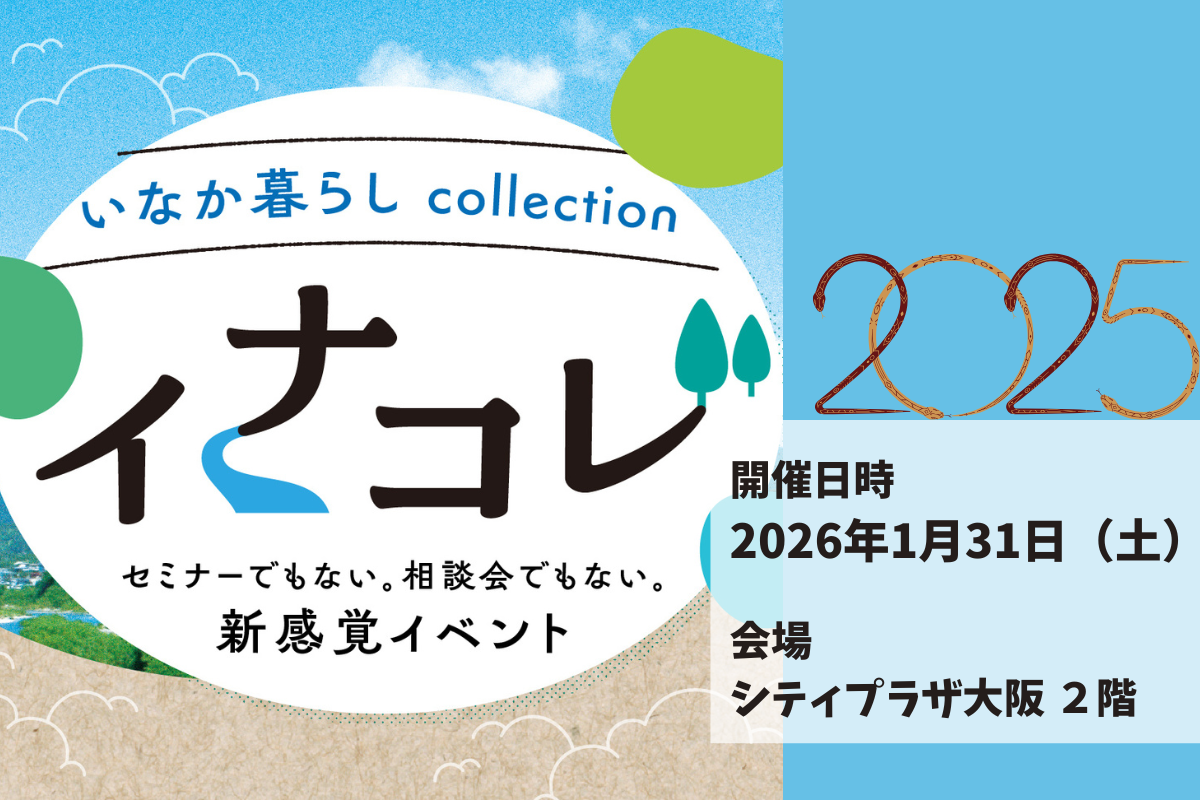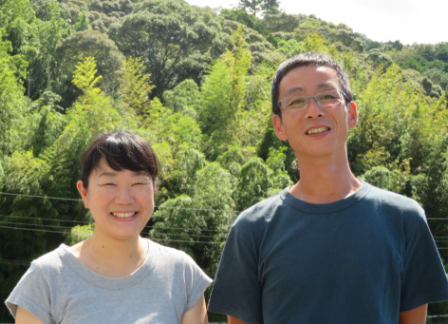【特集】地域おこし協力隊って、そもそもどのような制度?
- 掲載日:2025.10.22
- 気になる






一覧へ戻る

Q. 地域おこし協力隊にはどのような雇用形態がありますか?
A. 大きく二つに分類されます。自治体と雇用契約のある「雇用型」と雇用契約のない「委託型」です。
■雇用型
自治体と雇用契約を結ぶ形式です。隊員は自治体の会計年度任用職員として活動し、勤務時間や報酬などの条件は自治体の規則によります。隊員のサポート(活動面・生活面・精神面など)は自治体の担当者が行います。
■委託型
委託先企業と雇用契約を結ぶ形式です。隊員は委託先企業のもとで活動し、勤務時間や報酬などの条件は企業の規則によります。隊員のサポート(活動面・生活面・精神面など)は企業の担当者が自治体と連携して行います。
A. 協力隊は総務省による制度であり、平成21年度からスタートして15年以上の実績があります。令和6年度で7,910人の隊員が全国で活動していますが、地方への新たな人の流れを創出するため、総務省ではこの隊員数を令和8年度までに10,000人とする目標を掲げています。最近はテレビなどでも隊員として活動している方が取材されることもあり、地方移住への入口として人気のある仕事です。
A. 協力隊になるまでには、応募動機などの書類作成、一次面接、現地面接、最終選考などの選考があります。また、住民票の異動(移住)を伴うため、引越しの準備なども考慮すると、応募してから3ヶ月程度で着任するケースが多いです。ただし、随時募集しているケースもありますし、年度が変わって4月1日採用を希望しているミッションもあります。ミスマッチがないように事前に現地を訪問し、現地の方々ともしっかり会話することが大切です。早い段階から希望する自治体の担当者と密に連絡をとることをおすすめします。
A. 地域おこし協力隊への応募には一定の要件があります。
①年齢制限: 年齢制限がない自治体もありますが、18歳以上、20歳以上、50歳以下など下限や上限を設定している自治体もあります。
②住民票: 申込時点で、3大都市圏をはじめとする都市部等に住民票がある方かつ採用決定後に、活動地域に生活の拠点を移し、住民票を異動できる方
③語学能力: 日本語で日常的なコミュニケーションをとることができる方が対象となります。
④資格・経験: これらの要件は自治体により異なりますので、各自治体に問い合わせて確認することをおすすめします。一般的には、一定のPCスキルや運転免許を有していることを求められることがあります。
A. 自治体によって異なりますが、一般的には月給が「17万円~23万円」で設定されていることが多いです。その他に住宅補助・通勤手当・業務で使用する際の車両補助などをプラスしている市町村が多く見受けられます。
1年目、2年目、3年目で月給が変わるケースもあります。そのほかの待遇の詳細も市町村によって異なります。
A. 雇用型の場合は基本、自治体の規則に従う必要がありますが、最近では業務に支障の無い範囲で副業を許可している自治体も多くなってきています。委託型については委託先企業との調整次第となります。
A. 高知県は募集しているミッションの種類が多く、農林漁業(一次産業)から観光、商店街の活性化まで幅広い分野があり個々のニーズに合った活動が見つけられます。また、現役隊員・協力隊OB・OGの人数が多いためネットワークが強く、相談相手や任期終了後の良いロールモデルとなっています。そのような部分は全国的にも特徴的です。
A. 自治体が用意した公営住宅や職員住宅、空き家を使える場合が多いです。自治体によっては無償で貸与したり、家賃補助の支給があります。
A. 高知県では、地域おこし協力隊の任期終了後の定住率が73.7%(※)と全国平均の68.9%(※)を上回っています。その理由のひとつとして、任期中に多くの地域や企業の方と関わるため、その結果、地域での就職機会が増えることにつながっているという点があります。
※出典:総務省「令和6年度地域おこし協力隊の定住状況等に係る調査結果」
A. 高知県は交流が好きな県民性で、お祭りや食文化などを通じたコミュニケーションが盛んな地域です。地域イベント等への参加をきっかけに、自然と地域の方々との顔が広がります。また、市町村や移住支援団体等が「移住者交流会」を開催するなど、仲間を作りやすい環境なので心配は無用です。
.jpg)


最新の協力隊配置状況はこちら:https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025012300342/


地域おこし協力隊について解説いたします!

地域おこし協力隊という制度をご存知ですか?
都市部から地方の過疎地域等に住民票を異動して、地域のブランド力を向上させるための情報発信、イベントの企画・運営、一次産業の支援活動など様々な地域活動に取り組みながら、その地域への定住・定着を図る総務省の取り組みです。(実施主体は、各地方自治体となります。)任期は1〜3年で、その間は自治体から委嘱された公務員として任務にあたります。
令和6年度で7,910名の隊員が全国で活動しており、地方へ移住するための手段として認知度が上がってきています。
都市部から地方の過疎地域等に住民票を異動して、地域のブランド力を向上させるための情報発信、イベントの企画・運営、一次産業の支援活動など様々な地域活動に取り組みながら、その地域への定住・定着を図る総務省の取り組みです。(実施主体は、各地方自治体となります。)任期は1〜3年で、その間は自治体から委嘱された公務員として任務にあたります。
令和6年度で7,910名の隊員が全国で活動しており、地方へ移住するための手段として認知度が上がってきています。
今回は、そんな地域おこし協力隊について最低限おさえておきたいポイントや、隊員数全国1位(※)の高知県の取り組みなどについてご紹介します!
※人口10万人あたりの隊員数(令和6年度総務省調査)
※人口10万人あたりの隊員数(令和6年度総務省調査)
――――――――――――――――――――――――――
1.これだけは知っておきたい!地域おこし協力隊の基本
2.よくある質問・おさえておきたいポイント
3.地域おこし協力隊に挑戦するメリット
4.高知県は隊員数が全国1位!?
5.各種、支援制度について
――――――――――――――――――――――――――
これだけは知っておきたい!地域おこし協力隊の基本
地域おこし協力隊は、1〜3年間、都市部から地方に移り住み、地方自治体から「地域おこし協力隊」として委嘱を受け、地域の課題解決や活性化のための活動を行います。仕事内容や報酬は、隊員を募集している自治体によって異なりますが、どの自治体も共通して以下のような条件を設けていることが多いです。
<基本情報>
・給料…月17万〜23万円程度(各自治体により異なります)
・住居…無償貸与、家賃補助、住居紹介など
・働く場所…協力隊を募集している地方自治体
・仕事内容(ミッション)…さまざま(観光、地域づくり、一次産業などは特に多い)
・雇用形態…会計年度任用職員(自治体での直接雇用)、企業委託など
・雇用期間…最大3年間
・給料…月17万〜23万円程度(各自治体により異なります)
・住居…無償貸与、家賃補助、住居紹介など
・働く場所…協力隊を募集している地方自治体
・仕事内容(ミッション)…さまざま(観光、地域づくり、一次産業などは特に多い)
・雇用形態…会計年度任用職員(自治体での直接雇用)、企業委託など
・雇用期間…最大3年間
よくある質問・おさえておきたいポイント
早速、地域おこし協力隊についてよくある質問や最低限おさえておきたいポイントをご紹介します。Q. 地域おこし協力隊にはどのような雇用形態がありますか?
A. 大きく二つに分類されます。自治体と雇用契約のある「雇用型」と雇用契約のない「委託型」です。
■雇用型
自治体と雇用契約を結ぶ形式です。隊員は自治体の会計年度任用職員として活動し、勤務時間や報酬などの条件は自治体の規則によります。隊員のサポート(活動面・生活面・精神面など)は自治体の担当者が行います。
■委託型
委託先企業と雇用契約を結ぶ形式です。隊員は委託先企業のもとで活動し、勤務時間や報酬などの条件は企業の規則によります。隊員のサポート(活動面・生活面・精神面など)は企業の担当者が自治体と連携して行います。
Q. 知り合いに地域おこし協力隊がいないのですが、全国的に人気の仕事なんですか?
A. 協力隊は総務省による制度であり、平成21年度からスタートして15年以上の実績があります。令和6年度で7,910人の隊員が全国で活動していますが、地方への新たな人の流れを創出するため、総務省ではこの隊員数を令和8年度までに10,000人とする目標を掲げています。最近はテレビなどでも隊員として活動している方が取材されることもあり、地方移住への入口として人気のある仕事です。
Q. 地域おこし協力隊になるまでにはどのくらいかかりますか?
A. 協力隊になるまでには、応募動機などの書類作成、一次面接、現地面接、最終選考などの選考があります。また、住民票の異動(移住)を伴うため、引越しの準備なども考慮すると、応募してから3ヶ月程度で着任するケースが多いです。ただし、随時募集しているケースもありますし、年度が変わって4月1日採用を希望しているミッションもあります。ミスマッチがないように事前に現地を訪問し、現地の方々ともしっかり会話することが大切です。早い段階から希望する自治体の担当者と密に連絡をとることをおすすめします。
Q. 地域おこし協力隊は誰でも応募できますか?
A. 地域おこし協力隊への応募には一定の要件があります。
①年齢制限: 年齢制限がない自治体もありますが、18歳以上、20歳以上、50歳以下など下限や上限を設定している自治体もあります。
②住民票: 申込時点で、3大都市圏をはじめとする都市部等に住民票がある方かつ採用決定後に、活動地域に生活の拠点を移し、住民票を異動できる方
③語学能力: 日本語で日常的なコミュニケーションをとることができる方が対象となります。
④資格・経験: これらの要件は自治体により異なりますので、各自治体に問い合わせて確認することをおすすめします。一般的には、一定のPCスキルや運転免許を有していることを求められることがあります。
Q. 地域おこし協力隊の平均的な初任給はいくらですか?
A. 自治体によって異なりますが、一般的には月給が「17万円~23万円」で設定されていることが多いです。その他に住宅補助・通勤手当・業務で使用する際の車両補助などをプラスしている市町村が多く見受けられます。
1年目、2年目、3年目で月給が変わるケースもあります。そのほかの待遇の詳細も市町村によって異なります。
Q. 副業やミッション以外の活動をしてもいいですか?
A. 雇用型の場合は基本、自治体の規則に従う必要がありますが、最近では業務に支障の無い範囲で副業を許可している自治体も多くなってきています。委託型については委託先企業との調整次第となります。
Q. 高知県の協力隊は、他県と比べてどんな違いがありますか?
A. 高知県は募集しているミッションの種類が多く、農林漁業(一次産業)から観光、商店街の活性化まで幅広い分野があり個々のニーズに合った活動が見つけられます。また、現役隊員・協力隊OB・OGの人数が多いためネットワークが強く、相談相手や任期終了後の良いロールモデルとなっています。そのような部分は全国的にも特徴的です。
Q. 住まいは自分で探す必要がありますか?
A. 自治体が用意した公営住宅や職員住宅、空き家を使える場合が多いです。自治体によっては無償で貸与したり、家賃補助の支給があります。
Q. 高知県で協力隊を経験した人の定住率は高いですか?
A. 高知県では、地域おこし協力隊の任期終了後の定住率が73.7%(※)と全国平均の68.9%(※)を上回っています。その理由のひとつとして、任期中に多くの地域や企業の方と関わるため、その結果、地域での就職機会が増えることにつながっているという点があります。
※出典:総務省「令和6年度地域おこし協力隊の定住状況等に係る調査結果」
Q. 県外から移住する場合、地域になじめるか不安です。
A. 高知県は交流が好きな県民性で、お祭りや食文化などを通じたコミュニケーションが盛んな地域です。地域イベント等への参加をきっかけに、自然と地域の方々との顔が広がります。また、市町村や移住支援団体等が「移住者交流会」を開催するなど、仲間を作りやすい環境なので心配は無用です。
.jpg)
地域おこし協力隊に挑戦するメリット
地域おこし協力隊の活動は、一般の企業などで働くこととは大きく異なる点があります。 ここでは、その主なポイントをご紹介します。■地域に貢献できる
自分のアイデアや行動が地域の変化に直結するやりがい、自分が関わった提案やプロジェクトが実現する様子を間近で見ることができます。■自由度の高さ
自分の経験や得意なことを活かした活動が可能です。今までやりたかったけど、なかなか一歩が踏み出せないという方も活動期間中に挑戦できるチャンスがあります。
自分の経験や得意なことを活かした活動が可能です。今までやりたかったけど、なかなか一歩が踏み出せないという方も活動期間中に挑戦できるチャンスがあります。
■都会ではできない経験
自然に囲まれた暮らし、伝統行事への参加、新しい人との出会いなど、地方ならではの経験ができます。人と人との距離が近く、知らない人とも自然と仲良くなれるのは、都会には無い魅力です。
自然に囲まれた暮らし、伝統行事への参加、新しい人との出会いなど、地方ならではの経験ができます。人と人との距離が近く、知らない人とも自然と仲良くなれるのは、都会には無い魅力です。
■スキルアップ
企画力、発信力、地域マネジメント力など幅広い能力が身につきます。良い意味で多くを任せてもらえる環境があるため、活動期間中に得られる経験は今後の人生にきっと役立つでしょう。
企画力、発信力、地域マネジメント力など幅広い能力が身につきます。良い意味で多くを任せてもらえる環境があるため、活動期間中に得られる経験は今後の人生にきっと役立つでしょう。


高知県は隊員数が全国1位!?
実は、地域おこし協力隊の数が全国1位(※)の高知県。令和6年度の導入状況は過去最高の289名となっています。そんな高知県では、隊員のスキルアップを目的とした研修制度や隊員をサポートするための相談体制が整っていることが強みとなっています。任期終了後を見据えて、初年度から手厚いサポートを受けることができます。 ※人口10万人あたりの隊員数(令和6年度総務省調査)最新の協力隊配置状況はこちら:https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2025012300342/

各種、支援制度について
高知県では地域おこし協力隊の卒業後に起業や継業などをする際の支援制度があります。ここではその制度をご紹介いたします。
<高知県の協力隊研修制度・相談体制>
●研修会
・初任者勉強会(おおむね着任1年未満の協力隊対象)
・交流勉強会(全員対象)
・試作品販売会
・四国の地域おこし協力隊等交流勉強会
・キャリア形成支援研修(全員対象)
●相談体制
・県地域おこし協力隊相談窓口(OBOGが対応)
・国地域おこし協力隊サポートデスク(OBOGの専門相談員が対応)
●高知県地域おこし協力隊ネットワーク「とさのね」による支援
高知県内の地域おこし協力隊の活動支援と、現役隊員やOB・OGとのネットワーク形成を目的に、OBOG隊員等により構成される「地域おこし協力隊ネットワーク"とさのね"」が、隊員等を対象とした研修や、隊員からの相談対応、受入自治体への支援などを行っています。
サイトURL:https://tosanone.com/
●研修会
・初任者勉強会(おおむね着任1年未満の協力隊対象)
・交流勉強会(全員対象)
・試作品販売会
・四国の地域おこし協力隊等交流勉強会
・キャリア形成支援研修(全員対象)
●相談体制
・県地域おこし協力隊相談窓口(OBOGが対応)
・国地域おこし協力隊サポートデスク(OBOGの専門相談員が対応)
●高知県地域おこし協力隊ネットワーク「とさのね」による支援
高知県内の地域おこし協力隊の活動支援と、現役隊員やOB・OGとのネットワーク形成を目的に、OBOG隊員等により構成される「地域おこし協力隊ネットワーク"とさのね"」が、隊員等を対象とした研修や、隊員からの相談対応、受入自治体への支援などを行っています。
サイトURL:https://tosanone.com/
<高知県の起業支援>
●こうちスタートアップパーク
起業に関して、段階に応じたメンターが相談対応。入門から実践までの各段階で起業に関して学べるセミナーを開催。
サイトURL:https://startuppark.org/
●土佐まるごとビジネスアカデミー
ビジネスを進めるうえで必要な基礎知識から、応用・実践力まで「まるごと」学べる研修を開講。
サイトURL:https://www.kocopla.jp/tosamba/course.html
●こうちスタートアップパーク
起業に関して、段階に応じたメンターが相談対応。入門から実践までの各段階で起業に関して学べるセミナーを開催。
サイトURL:https://startuppark.org/
●土佐まるごとビジネスアカデミー
ビジネスを進めるうえで必要な基礎知識から、応用・実践力まで「まるごと」学べる研修を開講。
サイトURL:https://www.kocopla.jp/tosamba/course.html
<高知県の農林業研修・支援制度>
●高知県立農業担い手育成センターでの研修
農業の基礎から機械操作、経営管理まで幅広く学べる研修を実施。オンライン講座や1泊2日の体験型短期研修、長期研修など、目的に応じて選択可能です。
サイトURL:https://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/?sid=2011
●林業労働力確保支援センターでの研修
森林・林業や木造建築に関する講座から、クレーン・チェーンソーなどの資格取得講習まで幅広く実施。短期(1日〜1週間程度)の受講が可能で、初心者から実務者まで学ぶことができます。
サイトURL:https://www.shien-center39.com/
●就農に関する支援制度
49歳以下を対象に、就農準備資金(年150万円・最長2年)や経営開始資金(年150万円・最長3年)を交付。さらに県独自の上乗せ支援もあり、34歳以下なら年60万円の補助が受けられる制度も整っています。
●高知県立農業担い手育成センターでの研修
農業の基礎から機械操作、経営管理まで幅広く学べる研修を実施。オンライン講座や1泊2日の体験型短期研修、長期研修など、目的に応じて選択可能です。
サイトURL:https://www.nogyo.tosa.pref.kochi.lg.jp/?sid=2011
●林業労働力確保支援センターでの研修
森林・林業や木造建築に関する講座から、クレーン・チェーンソーなどの資格取得講習まで幅広く実施。短期(1日〜1週間程度)の受講が可能で、初心者から実務者まで学ぶことができます。
サイトURL:https://www.shien-center39.com/
●就農に関する支援制度
49歳以下を対象に、就農準備資金(年150万円・最長2年)や経営開始資金(年150万円・最長3年)を交付。さらに県独自の上乗せ支援もあり、34歳以下なら年60万円の補助が受けられる制度も整っています。


オススメコンテンツ
-
移住コンシェルジュについて
高知暮らしをお考えのみなさまのご相談を承ります!
-
インタビュー
移住までの経緯や高知での生活の様子、地元の方に思いなどを聞きました。
-
多様な働き方
企業就職以外の『高知ならではの多様な働き方』をご提案します。
-
イベントスケジュール
高知県へのUIターンに関するイベントや移住者向け交流会の情報を掲載しています。
イベント情報や支援情報など、
最新の情報をメールでお知らせします!


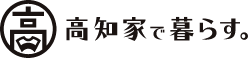
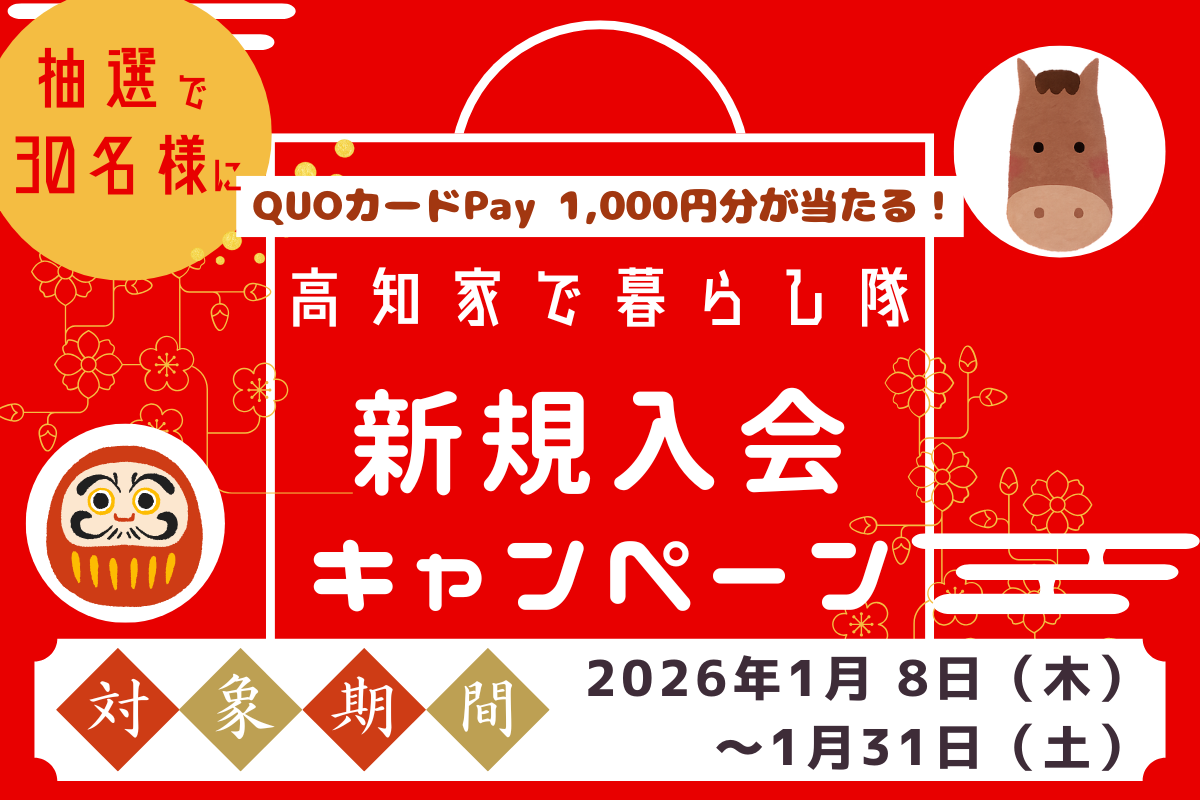


.png)